【苦手な人対象】実習中の質問内容の考え方手順2つ
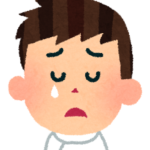
・「何か質問ある?」がイヤすぎる
・質問内容を考えるのに気をとられて、見学内容おぼえてない
・そもそも、何を聞いたらいいのかわからない
こんなお悩みを解決します
本記事の内容
・学びある質問をするための具体的手順2つ
・印象的シーンがみつからない方へ
・まとめ
本記事の信頼性
この記事を書いている私は

・作業療法士 10年目
・転職回数 2回 (病院2施設・訪看ステーション1施設)
・大学院修士課程修了
・実習指導人数 10名以上 (CV含め)
学生時代からうまくいかず挫折を多く経験してきました
それでも立ち直ろうと、困難に立ち向かったり、時には逃げてきました
今では訪看ステーションで自分らしく仕事をしています
夢だった養成校での講師のお仕事もいただけるようになりました
そういった僕が解説していきます。
学びある質問をするための 具体的手順2つ

ここでは、学びある質問をするための手順を説明します。
多くのOTSはこの手順を踏めば、質問ができるようになります。
手順は以下の2つです。
①治療場面で印象的なシーンを選ぶ
②選んだシーンで一番気になった部分をさらに分析する
これから、手順の詳細について説明します
①治療場面で印象的なシーンを選ぶ
すべての場面に対して質問を考えていると、
肝心な場面を見逃してしまうリスクがあります。
そういったリスクを回避するために
印象的なシーンを選ぶことが大切です。
印象的なシーンの選び方は簡単です。
それは「問いかけをすること」です。
見学中、下のような問いかけを「自分に」してみてください。
・なんでこうなるんだろう?
・なんでこうするんだろう?
・どうやって判断したんだろう?
その問いかけの答えが自分で
「思い浮かばない」もしくは、
「思い浮かぶけど、モヤモヤする」場合は
印象的なシーンとして更に頭で考えて分析しましょう。
見学終了後にOTRに質問すれば、アナタの学びになります。
②選んだシーンで一番気になった部分をさらに分析する
選んだシーンで疑問に感じたことを、
そのままOTRに質問すると、学びになりません。
アナタなりに分析したことを添える事がとても重要です。
学びのある質問にするために、分析をしていきましょう。
分析の方法は、アナタがどこに疑問を感じたかによって変わります。
①患者さんの動きや言動
②OTRの言動
③OTRの治療内容
上の3つの内、一番強く疑問を感じた部分はどれでしょうか?
選んだ部分に対して、さらに分析をしていきましょう。
患者さんの動きや言動の場合
すべての出来事には「原因」と「結果」があります。
見学中に見えることは主に「結果」です。
学びある質問をするためには、「原因」を考える必要があります。
患者さんの動きや言動の「原因」はなんでしょうか?
その「原因」を考えて、OTRに質問すればOKです。
具体例を交えて解説していきます。
<患者さんの動きや言動>
病室のベッドからの起立が不安定である
この場合の原因を考えていきましょう。
まず、なぜ起立が不安定になるのでしょうか?
その原因の候補を考えます。
疾患の影響? 筋力のせい? 感覚のせい? 環境のせい? ・・・
アナタが得られる情報を活用して、その原因の候補を絞りましょう。
筋力が原因と考えたのなら、質問はほぼ完成です。
例えば以下のような質問内容が浮かぶはずです
①この方の起立動作が不安定な原因は、「筋力」にあると考えたのですがいかがでしょうか?
②この方の起立動作が不安定な原因は「筋力」と考えましたが、先生はどのような手順で評価されたのですか?
①の質問でも全く問題ありません。
しかし②の質問の方が、OTRの頭の中を覗けますね。
同じ質問内容であったとしても、
質問の仕方によって、OTRから返ってくる情報は変わります。
OTRの言動の場合
OTRがなぜその言動をしたのか?
その「理由」と「目的」を探ることが必要です。
アナタが得られる情報を使って、
その「理由」と「目的」を推測してみましょう。
具体例を使って解説します。
<OTRの言動>
いつも言葉遣いと説明が丁寧なOTRなのに、この患者さんには簡潔な言葉を使っている
この場合の「理由」と「目的」を考えてみましょう。
なぜ丁寧な言葉づかいをするのでしょう?
丁寧な言葉づかいには、相手からの信頼感を得やすいメリットがあります。
しかしその反面、「他人行儀」、「まわりくどい」といったデメリットがあります。
もしかすると、OTRは
「簡潔な表現」で「わかりやすさ」を重視したいのかもしれません。
質問の具体例を挙げてみます
①先生がこの方に、簡潔な表現をあえてしている理由は「わかりやすさ」を重視しているからでしょうか?
②先生が患者さんに対して言葉づかいや説明方法を変えておられますが、どのように使い分けておられますか?
①の質問は具体的な回答が得られます。
②の質問は①よりもやや抽象的な内容になっています。
OTRの治療内容の場合
OTRがなぜその「治療」をしているのか?
「選択理由」「注意点」「効果判定」の3点を中心に
分析してみると、頭の中が整理しやすいです。
具体例で解説します。
<OTRの治療>
パーキンソン病の患者さん、起立動作は上肢で引っ張りながら行っている。
OTRは座位で骨盤のあたりを触っている。前の方に動かしていそう。
骨盤を前の方に動かしているのでは? と考えました。
次にすべきは、「選択理由」「注意点」「効果判定」の3つです。
下の表にまとめてみました。
<選択理由>
骨盤を前傾させたいから?
<注意点>
外から見る分にはわからない・・・
<効果判定>
起立動作で確認する?
上の表をもとにすると、色々な質問が作れます。
<選択理由への質問>
①先生が、患者さんの骨盤を触っておられましたが、それは骨盤を前傾させたいからですか?
<注意点への質問>
②骨盤を前方に誘導していたあの場面で、先生が注意している点はどのようなものですか?
<効果判定への質問>
③骨盤を前方に誘導した後、起立動作以外でどのように効果判定を行っていますか?
④起立動作の中で、どの点に着目して効果判定を行っていますか?
「選択理由」「注意点」「効果判定」の3つで分析すると、
質問はこれ以外にも、たくさん思い浮かぶはずです。
印象的シーンがみつからない方へ

どうしても印象的なシーンがみつからない。
どうしたらいいの?と悩む方へ
多くの場合は、アナタが漠然と見学していることが原因です。
見学中に「なんで?」と自分に問いかける頻度を増やしてください。
極端な話で言うならば、
「なんで座ったまましてるの?」
「なんで立った状態でしているの?」
「なんで上肢から触るの?」
こんな単純な問いかけからでもOKです。
どんどん自分に問いかけてください。
問いかけをすればするほど、
アナタの眼は成長していきます。
まとめ

今回は、皆さんが苦手な「質問」を得意に変える方法を説明しました。
質問内容の考え方手順を紹介しました。
①治療場面で印象的なシーンを選ぶ
②選んだシーンで一番気になった部分をさらに分析する
また、印象的なシーンをどうしても選べない方に、
その対策方法を提案しました。
どんな簡単な問いかけでもいいので
「なんで?」と問い続けてください。
別記事で、
質問テンプレートと質問の意味について解説しています。
よければご覧ください。
質問は、アナタの知識や技術を大きく成長させるものです。
有意義な実習が送れるよう願っています。

